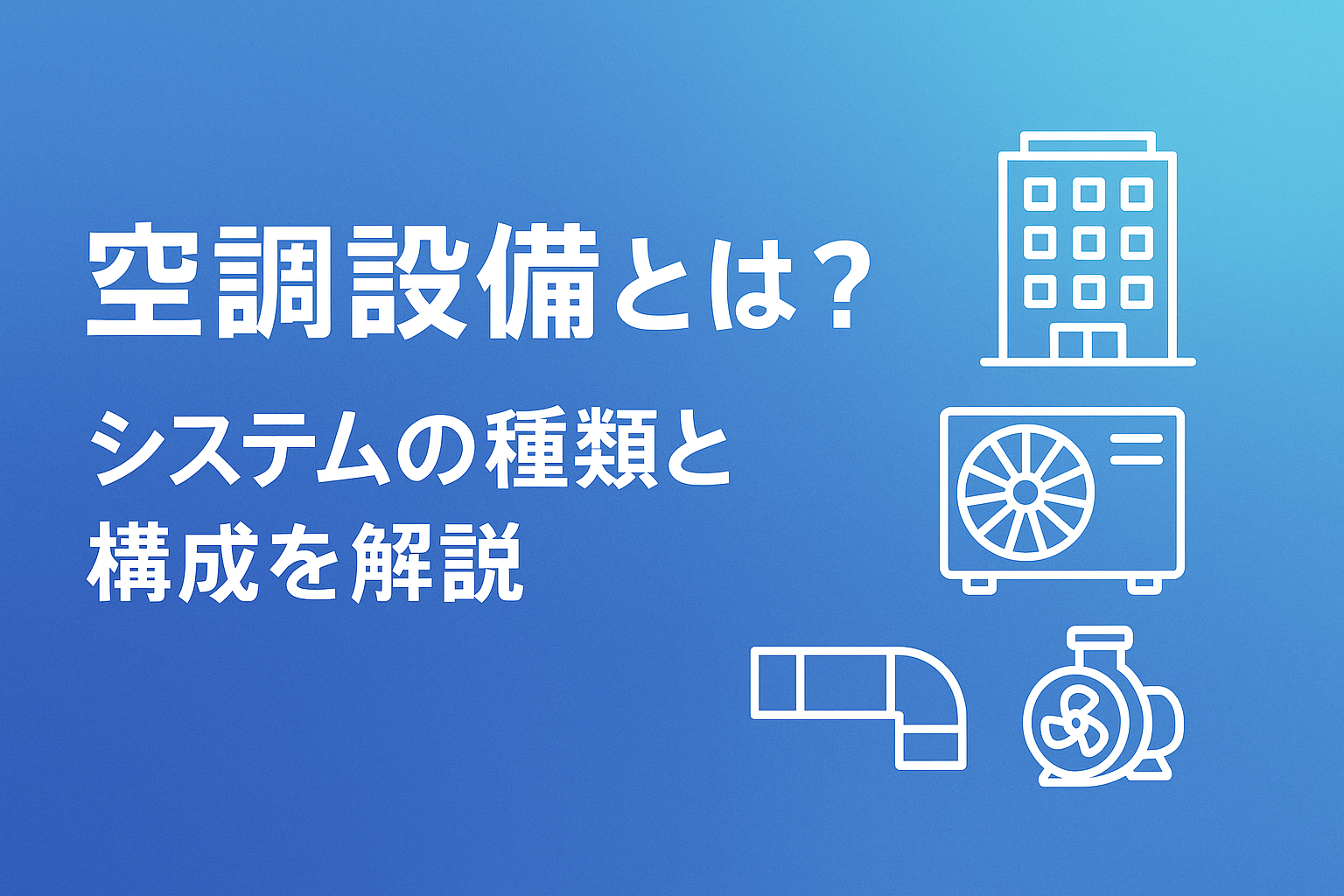
空気調和設備(以下、空調設備)は、快適な室内環境を維持するために不可欠な存在ですが、導入の際にはコスト面とのバランスも慎重に考えなければなりません。
とはいえシステムや構成が専門的で、製品選びにお悩みの企業様もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では空調設備とは何かという点を説明し、あわせてシステムの種類や設備の構成についても触れていきます。
導入を検討する際の基礎知識として、ぜひ最後までご覧ください。
空調設備とは、室内の空気の状態を整える装置やシステムのことです。
厚生労働省では、“建築物における衛生的環境の確保に関する法律”に基づき、空調設備を以下のように定義しています。
空気調和設備とは、「エア・フィルター、電気集じん機等を用いて外から取り入れた空気等を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)することができる機器及び附属設備の総体」をいいます。
引用元:厚生労働省「建築物環境衛生管理基準について」
空調設備は、温度・湿度・気流・空気中の微粒子などを総合的に管理し、快適かつ衛生的な空間を維持する役割を担います。
繰り返しになりますが、空調設備は空気を整えることで、快適で清潔な室内環境を保つ役割を果たしています。
この役割は、空気そのものが人の生命維持に欠かせない存在であるからこそ非常に重要です。
人が体内に取り込む空気のうち約6割が室内空気であることから、屋内の空気を良好に保つことは、健康維持や体調管理の面でも欠かせない要素なのです。
多くの方は“空調設備”と聞くと、エアコンや換気設備をイメージしがちですが、これらとは役割や機能が異なります。
空調設備とエアコン、そして換気設備の違いを表にまとめたので、まずは以下をご覧ください。
【空調設備・エアコン・換気設備の比較表】
| 項目 | 空調設備 | エアコン | 換気設備 |
| 役割 | 温度・湿度・気流の調整、換気を一元的に行う設備 | 温度・湿度・気流を調整する設備 | 室内の汚れた空気を排出し、新鮮な空気を取り入れる設備 |
| 法的分類 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律で定義されている空調設備 | 単体では空調設備に該当しない | 単体では空調設備に該当しない |
| 温湿度調整機能 | あり | あり | なし |
| 気流調整機能 | あり | あり | なし |
| 換気機能 | あり | なし | あり |
エアコンは、空調設備に備わっている機能のうち、換気機能がないものを指します。
反対に、換気設備には、温度や湿度を調整する機能が備わっていません。
これら2つは、単体では法的に空調設備とはいえないことがわかります。
関連記事:業務用エアコンに換気機能はある?換気の種類や方法も紹介
空調設備は、“対人空調”と“産業用空調”の2種類に分けられます。
それぞれの設置される環境や目的を、以下で詳しく解説します。
オフィスビルや商業施設、ホテル、病院、学校などで主に導入されているのが、対人空調です。
これらの、人が日常的に利用する建物では、滞在する方が快適かつ健康的に過ごせるように空気環境を整える必要があります。
対人空調は、建物内の空気を適切に管理し、利用者の快適な生活環境と健やかな状態を維持することを目的としています。
【関連記事】ビル用マルチエアコンとは?メリットと注意点・選び方を解説
産業用空調は、工場や倉庫、農園芸施設、データセンターなどの施設で利用されます。
たとえば、工場や倉庫では温湿度管理によって製品の品質を保持し、農業施設では作物の生育環境を整える役割を担っています。
また、データセンターでは、機器の発熱を抑えて端末やシステムの機能を正常に保つのに産業用空調が不可欠です。
さらに、これらの施設で働く方の作業環境の維持も、産業用空調を導入する重要な目的の一つです。
暑さや寒さが厳しい環境下での体調管理に重要な役割を果たし、安全に働ける環境づくりにも寄与しています。
ここからは、空調設備システムの2つの種類について解説します。
導入を検討している施設に、どの種類の空調設備が適しているのか見極めるための判断材料としてください。
セントラル空調方式(中央空調方式)とは、建物全体の空調を一元的に管理するシステムのことです。
冷凍機やボイラーなどの熱源機を中央の機械室や管理室に集約し、そこで生成された冷温水を建物内に循環させることで各空間の温度調整を行います。
建物内の空調を一括管理できるため、フロアや部屋ごとに温度のばらつきが出ないのが長所です。
また、複数の熱源機が一か所に集中していることから、保守点検や設備管理も比較的容易に実施できます。
このような特徴から、使用時間や温度設定を建物全体である程度共有できる、大規模なオフィスビルや総合病院などの施設で多く採用されています。
パッケージ方式(個別空調方式)は、各フロアや部屋単位で空調設備を設置し、それぞれ独立して運転を行う方式です。
空気中の熱を汲み上げて別の場所に移動させるヒートポンプ技術を活用し、冷媒を用いて空気を冷却または加熱します。
この方式は、空調が必要な場所に直接設備を設置できるのが特徴です。
フロアや部屋ごとで空調設備のオンオフを切り替えられるため、エネルギーの無駄な消費を防ぎ、効率的な運転が可能になります。
このような特性から、パッケージ方式は、営業時間や使用目的が異なる複数のテナントが入居する、中小規模の商業施設やテナントビルに適しています。
空調設備は大きく分けて、熱源機・熱搬送設備・空調機の3つの装置によって構成されており、これらが連動して室内の空気を整えます。
それぞれの装置の役割は、以下の通りです。
【熱源機・熱搬送設備・空調機の役割】
装置 | 役割 |
熱源機 | ・加熱や冷却に必要な熱エネルギーを生み出す ・ボイラーやヒートポンプ、冷却塔、冷却水ポンプ、給水設備などがある |
熱搬送設備 | ・熱源機で生成した熱エネルギーを、空調機へ届ける ・配管やダクト、ポンプ、送風機などがある |
空調機 | ・温度・湿度の調整や空気の浄化を行い、その空気を送り出す ・加湿器や除湿器、コイル、エア・フィルターなどがある |
このように、快適な空間をつくるには、それぞれの装置の役割との連携が不可欠ということがおわかりいただけたのではないでしょうか。
前項で紹介した装置に加え、空調設備には、“熱交換器”とよばれる機器も含まれています。
熱交換器とは、温度の違う気体のあいだで熱を移動させる装置のことです。
ヒートポンプのように空気の温度そのものを変えるのではなく、熱だけを移動させる点が特徴です。
空調設備は、熱交換器に用いられる熱の運び手(気体や液体)によって次の4つに分けられます。
【熱交換器による4つの分類】
全空気方式は、空気を主な熱の運び手とするため、安全性が高く、環境への負荷も少ないのが特徴です。
セントラル空調方式が採用されているケースが多く、部屋ごとの細かな温度・湿度調節には向きませんが、建物全体の効率的な空調管理には非常に適しています。
水を主な熱の運び手とする吸収式ヒートポンプを使用したものが、全水方式です。
給気や排気、換気などを行う“ダクト”を収めるためのダクトスペースは不要ですが、室内の空気を新鮮に保てるように窓の開放や換気設備が必要です。
空気・水併用方式は、熱を移動させるのに空気と水を活用し、状況に応じて自動的に切り替えられる方式です。
全空気方式と比べて設置スペースが抑えられるほか、空気と水で役割を分担することで、効率的な運転と快適な空調環境の両立が可能になります。
冷媒方式にはフロンガスと、電気の力で冷媒を圧縮して温度を変える圧縮型ヒートポンプが使用されています。
住宅や小規模なオフィス向けの、標準的なエアコンに多くみられるタイプです。
ここからは、空調設備の利用に欠かせないメンテナンスについて見ていきましょう。
以下では、メンテナンスが必要な理由や点検方法を解説します。
長期間にわたり空調設備を適切な状態で維持し、快適な室内環境をつくるためには、定期的な点検や清掃などのメンテナンスが欠かせません。
メンテナンスを怠ると、本来の性能が低下して無駄な電力を消費してしまううえに、冷暖房の効率が落ちるリスクも生じます。
こまめな手入れを行えば、空調設備を効率的に稼働させられるため、電気代の節約につながるほか、耐用年数いっぱいまで安全に使用できるようになるでしょう。
さらに、空調設備が正常に動作すればカビの発生も防ぐことが可能で、室内の快適さを保ちやすくなります。
このように、定期的なメンテナンスは設備の性能維持と快適な環境づくりのために非常に重要です。
空調設備のメンテナンス・点検を行う際は、以下の3つのポイントを目視で確認しましょう。
【空調設備のメンテナンス・点検で確認したいポイント】
まず室外機では、破損や錆びつきがないか、また運転時に異音や振動がないかをチェックします。
室内機については、室外機と同様のチェック項目のほかに、異臭が発生していないかどうかもご確認ください。
そして、空調設備全体としては、冷暖房の効きが悪かったり、電源を入れても動作しなかったりしないか確認が必要です。
これらの点検で異常を発見した場合は、速やかに専門業者のメンテナンスを受けることをおすすめします。
ここまでお読みいただき、「空調設備の導入・入れ替えを本格的に検討しよう」とお考えになった企業様もいらっしゃるでしょう。
そこで以下では、空調設備を選ぶ際に押さえておきたい2つの注意点をお伝えします。
空調設備を選ぶ際は、以下の3つの耐用年数をチェックしましょう。
【3つの耐用年数】
上記のうち、法定耐用年数は、税務上の減価償却を計算するために国によって定められた期間であり、任意に変更することはできません。
実質的な耐用年数を把握するには、法定耐用年数を除いた2つの耐用年数の期間を確認することが大切です。
物理的耐用年数は経年劣化によって性能が大きく低下するまでの期間を示し、経済的耐用年数は修理費の増加により、経済的に使いつづけるのが難しくなるまでの期間を指します。
これらは、“故障寿命”や“耐用寿命”ともよばれ、適切なメンテナンスや日常の点検をきちんと行えば、延ばすことも可能です。
初期費用だけでなく、メンテナンスや修理などの費用を含めた資金計画を立てるためにも、耐用年数はきちんと押さえておく必要があります。
毎月の電気代をはじめ、メンテナンス費用や消耗品の交換費用など、空調設備の利用にかかるランニングコストは、中長期的な視点でみることが肝要です。
特にメンテナンス費用を削減しようと、整備や点検をおろそかにしてしまうと、故障の頻度が増し、結果として修理や機器の交換により高額の費用がかかることがあります。
こうした事態を避けるために、コストは目先の節約だけでなく、中長期的な視点で捉え、計画的なメンテナンスの実施が重要です。
これにより、無駄な出費を抑えつつ空調設備を長く安全に使いつづけられます。
今回は、空調設備のシステムの種類や設備の構成について解説しました。
空調設備とは、室内の空気の状態を整える装置やシステムのことです。
温度や湿度、気流、空気中の微細な粒子を総合的にコントロールし、快適で清潔な空間を保つ役割を果たします。
空調設備には、オフィスビルや商業施設などに適した対人空調と、工場や倉庫で利用される産業用空調の2種類があります。
これらの違いを押さえつつ、導入する場所に適したものを選びましょう。
「プロに相談しながら空調設備を選びたい」という企業様は、エアコン卸センターにぜひご相談ください。
業務用エアコン専門の技術者が、お客様のニーズに合った空調設備をご提案させていただきます。
■エアコン卸センターのチラシはこちら
業務用エアコンの激安販売・取付・交換工事はエアコン卸センター
【対応エリア】
・東京の業務用エアコン販売、設置・交換工事
・神奈川の業務用エアコン販売、設置・交換工事
・千葉の業務用エアコン販売、設置・交換工事
・埼玉の業務用エアコン販売、設置・交換工事
・名古屋の業務用エアコン販売、設置・交換工事
・大阪の業務用エアコン販売、設置・交換工事
・福岡の業務用エアコン販売、設置・交換工事
この記事の監修者

物販、飲食、事務所など商業施設をメインに20年以上空調設備工事に携わらせていただきました。
近年の猛暑の影響もあり、インフラとしての重要性が益々高まってきております。
これまで培ってきたスキルと経験を元に、空調設備工事をより迅速により正確に行いたいと考えております。